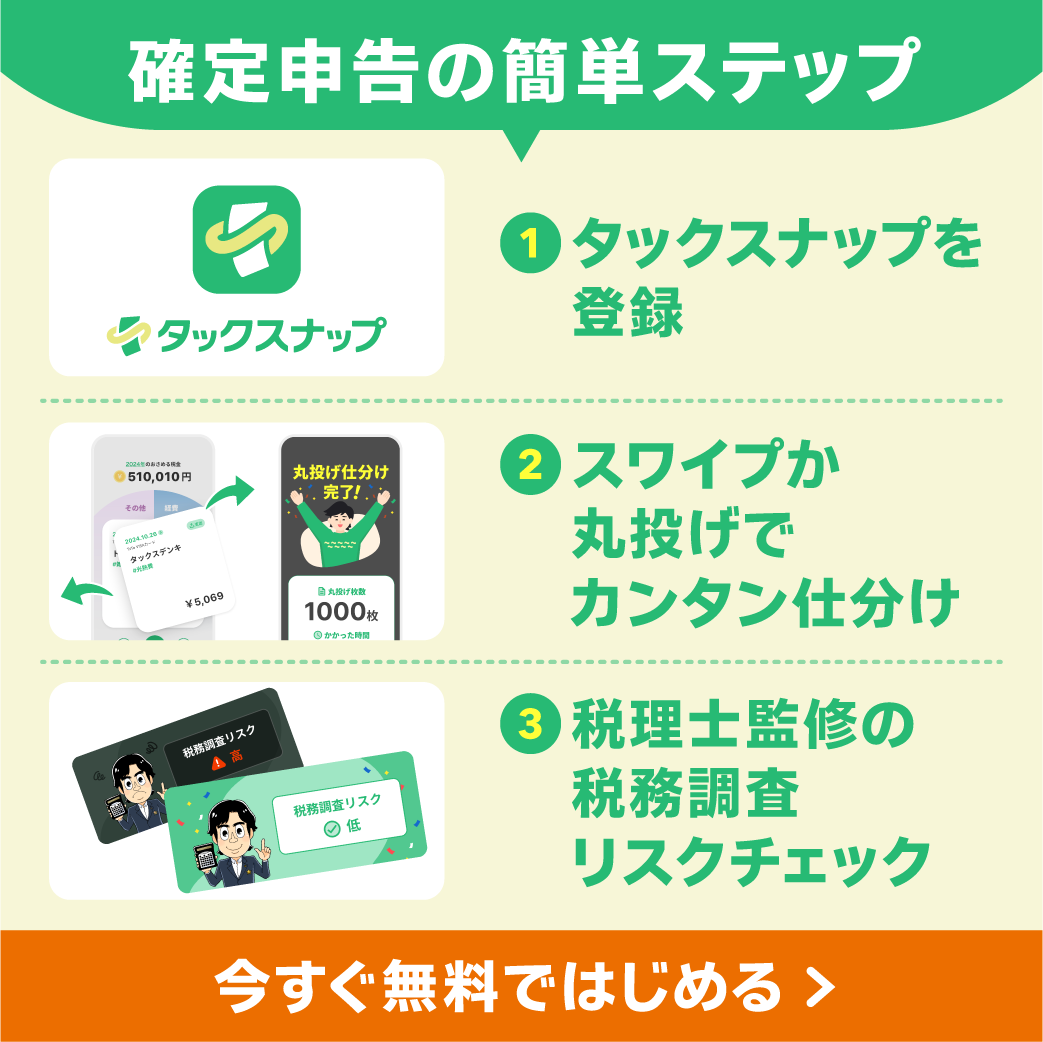コラム– category –
-

赤字でも経費は青色申告の繰越損失で計上!条件や申告方法を解説!!
事業が思うように利益を上げられず、赤字になってしまった――そんなときでも、経費を正しく計上し、青色申告をしておけばチャンスがあります。「繰越損失」という制度を使えば、赤字分を翌年以降の黒字から差し引いて、税金を減らすことができるのです。こ... -

開業届の「専従者」とは?意味・書き方・届出の注意点をわかりやすく解説
「開業届に“専従者”という欄があるけど、何を書けばいいの?」「家族が手伝っている場合はどうなる?」個人事業主として開業届を提出する際、よく出てくる疑問がこの「専従者」の扱いです。結論から言えば、専従者とは“生計を同じくする家族で、事業を主に... -

年間48万円以下でも開業届は必要?確定申告との関係をわかりやすく解説
「副業で少ししか稼いでいないけど、開業届は必要?」「年間48万円以下なら税金がかからないって聞いたけど本当?」個人で仕事を始めたとき、まず気になるのが「開業届と確定申告の関係」です。実は、所得(利益)が48万円以下でも開業届は出せますし、出... -

メルカリでバイクを売ったら確定申告は必要?課税対象と非課税の違いをわかりやすく解説
「使わなくなったバイクをメルカリで売ったけど、税金がかかる?」「確定申告って必要?」メルカリなどのフリマアプリでバイクを売る人が増えていますが、売却金額が大きいだけに「税務上どう扱われるのか」が気になるところです。結論から言うと、個人が... -

スキマバイトでも確定申告は必要?税金がかかる条件と申告の流れを解説
「スキマ時間に少しだけ働いても確定申告が必要?」「アプリで稼いだ収入って会社にバレる?」タイミー・Uber Eats・シェアフルなど、好きな時間に働ける“スキマバイト”は人気の働き方です。しかし、スキマバイトの収入も立派な“所得”として扱われ、条件に... -

メルカリ転売で確定申告するとき「在庫」はどう扱う?仕入れ・経費・在庫管理の基礎を解説
「メルカリで転売をしているけど、売れ残った商品(在庫)は経費になる?」「仕入れたけどまだ売れていない分はどう扱う?」確定申告で混乱しやすいポイントのひとつが「在庫の処理」です。結論から言うと、仕入れたけどまだ売れていない在庫分は、その年... -

開業届の「開業日」を未来の日付にしてもいい?正しい日付の決め方と注意点
「開業届を出したいけど、実際に仕事を始めるのは来月から」「準備中だけど、日付はいつにすればいい?」開業届に記入する“開業日”は、意外と多くの人が悩むポイントです。結論から言えば、開業届に未来の日付を書いて提出することは可能ですが、実務上は... -

開業届を郵送で提出する方法と封筒の書き方|控えの返送も忘れずに!
「開業届を出したいけど、税務署まで行く時間がない」「郵送で送っても受け付けてもらえるの?」そんな疑問を持つ個人事業主の方は多いでしょう。結論から言えば、開業届は郵送でも問題なく提出できます。ただし、封筒の書き方や同封書類に不備があると、... -

業務委託で働くときは開業届が必要?フリーランスが知っておくべき基礎知識
「業務委託契約を結んだけど、開業届を出す必要はある?」「フリーランス扱いと言われたけど何から始めればいい?」会社員から個人で働く形に変わると、まず悩むのが“開業届を出すかどうか”という点です。結論から言うと、業務委託で継続的に収入を得る場... -

クリエイターが開業届を出すときの「職業欄」はどう書く?記入例と注意点を解説
「フリーのデザイナーになったけど、開業届の“職業”欄って何て書けばいい?」「動画編集やイラスト制作など、複数の仕事をしている場合はどうするの?」クリエイターとして独立する際、最初の一歩となるのが「開業届」の提出です。しかし、職業欄や事業概...